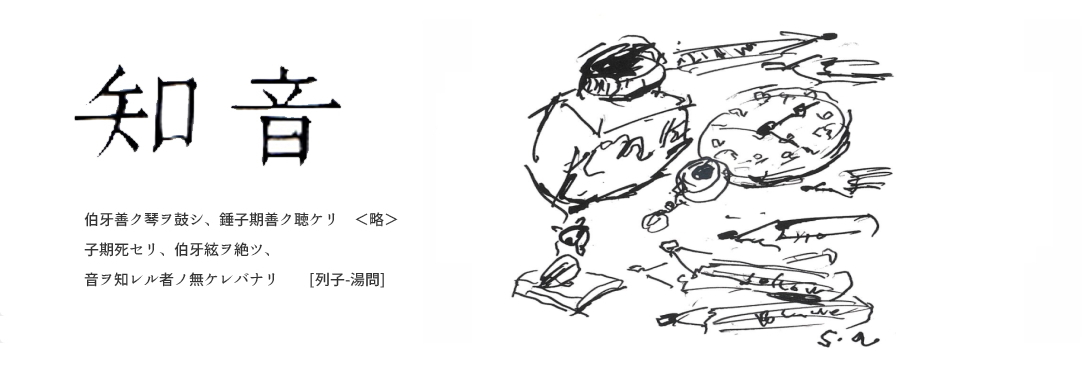駒返る草 西村和子
桃活けて離れ住む子の誕生日
山茱萸を挿頭し古墳の主や誰
紫木蓮ひとひら裏を覗かせし
春の風邪心地ふしぶしぎこちなく
亀鳴くや練塀長き綾小路
駒返る草に自転車乗り捨てて
ひもすがら鳴り響動むなり木の芽山
ゆくほどに耳朶こそばゆし芽吹山
桜 餅 行方克巳
寒牡丹まひるまの閨覗かるる
水影の声かうかうと鶴帰る
燕返し一太刀にしてやられたる
夏蜜柑内緒の話たのしくて
日月をつまぐるごとく彼岸婆
向島よりお持たせの桜餅
桜餅むけば冷たき夜のかをり
黒板に恋ほのめくや卒業期
辛夷咲く 中川純一
さきがけの辛夷に風のすさびけり
風船に吊り下げられしピエロかな
地虫出てすぐ草色にまぎれんと
春の出湯息子の軀分溢れ
ドアノブに大家さんより干若布
供へるとなく雛壇の若布汁
一摑みほどの花束卒業す
来年を約して共に浴びし花
◆窓下集- 5月号同人作品 - 中川 純一 選
竹馬や行くあてもなくただ闊歩
吉田しづ子
我が内にジギルとハイド去年今年
菊池美星
わが影をひたひた濡らす春渚
大村公美
明王の存外小さし初不動
大塚次郎
生涯を茶道に徹し足袋真白
山田まや
ちよつかいはいつも妹今朝の春
若原圭子
悴むやキャンセル通知捌きつつ
金子笑子
雪の香のはつかに兆し寒椿
島田藤江
夫の背のまろしと思ふ今朝の冬
池浦翔子
飛ぶ夢を見しより続く四温晴
竹見かぐや
◆知音集- 5月号雑詠作品 - 西村和子 選
あたたかき日の続きをり寒の入り
島田藤江
志とげたる朝梅真白
米澤響子
枯蘆の枯芒よりかろき音
井出野浩貴
月凍つる醜き我を窓へ嵌め
田中久美子
社への六十六段淑気満つ
井内俊二
マンションの下まで遠し冬籠
大橋有美子
参道のここも閉店春寒し
影山十二香
一投に一打に声援冬うらら
前山真理
寒肥や明日は雨の降るらしく
山﨑茉莉花
表札に旧き町の名鳥総松
藤田銀子
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
雪しんしんこのまま暮れてしまふのか
島田藤江
雪がしんしんと降っている。天候も一日もこのまま暮れてしまうのか、それだけのことを言っている句だが、この句からは人生の淋しさが伝わってくる。疫病流行という昨今の世の中の状況や、作者の八十代という年齢を考え合わせると、雪がしんしんと降り積もる一日の淋しさは想像に余りある。
「このまま暮れてしまふのか」という心の呟きは、このまま終わりを迎えるのかという人生の感慨にも及ぶような気がする。寒く静かな世の中の底で、人は人生を深く掘り下げて思うことがある。表向きはあくまでも一日の天候と時間を詠んでいる点がこの句の魅力を深めている。
理財にもメカにも疎く蕪汁
井出野浩貴
自画像であろう。理財すなわち金儲けにも、メカすなわち先進機械の操作にも疎い、そんな自分を認めながら、蕪汁をおいしいと啜っている。まだ五十代半ばの作者にしてみれば、努力次第で理財にもメカにも強くなるとは言わないまでも、一般の水準ぐらいにはなれるだろう。しかしこの季語が語っているのはそんなことではない。そんな自分の生き方や価値観をこれでいいのだと自嘲ぎみに諾っているふしがある。
「蕪汁」はけっして贅沢なものではない。しかし作ったこのある人はわかるだろうが、熱を入れすぎると柔らかくなりすぎ、蕪の甘みが損なわれやすい。本当においしく食べるのはひと冬でも数回である。歳時記によると、蕪は株が上がるようにと商売繁盛の縁起物としても好まれたようだ。そう考えて読み直すと、どことなくおかしみが湧いてくる。
夫術後我故障中寝正月
田中久美子
「寝正月」とは怠けて寝て過ごしているわけではなく、元来は病気で寝ていることを縁起を担いで表現した季語である。作者は今年まさにそのような新年を迎えた。夫は手術の後、自分は看病疲れが出て何もしないで正月を過ごしたのだろう。「我故障中」という表現に俳諧味があり救いもある。長い人生のうちにはこんなこともある。こんな時でもこうした佳句を詠みうることを称賛したい。