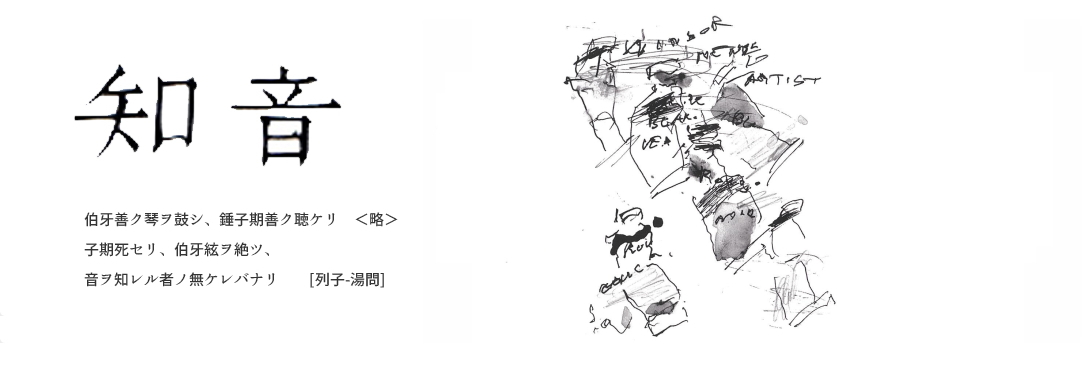冬帽子 行方克巳
独酌の酒は「死神」寒四郎
嚙みしめて白湯の甘さよ寒四郎
大根一本水の重さのただならず
桜鍋につちもさつちもいかねぇと
手つかずのままの一稿冬灯
その男セザンヌといふ冬帽子
雑踏に紛るるための冬帽子
寒 取 西村和子
玉肌のいよよ紅潮初相撲
初場所の行司朱房も穢無し
寒取の甲斐のありけり勝名乗
負けん気は強さうなれど初相撲
寒晴や吹かれて光る松の針
ゆくほどに冬芽ほのめく段葛
心願は畢竟ひとつ寒詣
箱根登山鉄道 中川純一
乗初の小田急線の窓に富士
我が好む珈琲豆を買初に
冬紅葉潜り湯屋への長廊下
氷下魚釣る穴にさらさら雪が降る
初場所の十両相撲めまぐるし
春を待つ茶髪京橋交差点
芽吹き山噛みつつつ登山電車かな
◆窓下集- 3月号同人作品 - 西村和子 選
その影の疎にして細か枯木立
小山良枝
足利学校ひねもす落葉掃きをらむ
井出野浩貴
花柊こぼれ門扉の閉ざされて
中野のはら
対岸の煙すぐ折れ冬霞
大橋有美子
阿弥陀堂裏へまはれば昼の虫
米澤響子
空港は淋しきところ神無月
佐貫亜美
近道のつもりが迷路返り花
廣岡あかね
託されし手紙速達菊日和
中津麻美
極月の雨や出がけの探し物
小倉京佳
岩窟に妖気たちこめ暮の秋
松枝真理子
◆知音集- 3月号雑詠作品 - 中川純一 選
十三個までは数へし烏瓜
米澤響子
海彦と山彦集ひ冬麗
佐瀬はま代
道産子にふんばる力豊の秋
小山良枝
ヘルメット残る廃坑山眠る
影山十二香
荒れ馬の眼澄みゆく枯野かな
井出野浩貴
冷やかや新聞めくり一人言
深澤範子
柊の花咲く頃のおもやつれ
馬場繭子
涼新た夫の寝癖の王の如
田中久美子
掛軸の黒熊とゐて冬ごもり
山田まや
初氷赤き実一つ閉ぢ込めて
清水みのり
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -中川純一
縄文の女神も民もしじみ汁
米澤響子
しじみ汁は旨いのみならずタンバク源として大切だ。そして時は縄文時代というと、まだ農耕も渡来しておらず、狩猟が主体で、動物を捕獲するのは危険も伴うし、道具も大変だ。その点、しじみは誰でも簡単に集めることができた。女神として祀られている像にもお供えをした信心深い古代の民を描いているところが心温まる句である。
日曜日当番医終へ秋惜しむ
深澤範子
歯科医院長である作者、個人病院だと日曜日は普通開いてないけれど、大きな病院の当番も担当しておられるようだ。毎日曜日ではないだろうが、そういう出勤日もある。私だったらなんとなく余分に働いた気分になるところだが、それが終わって、気持がほぐれると秋も終わりに近い空気を感じている。経験豊かな穏やかな人柄を感じる。
癖文字と言へど手書きの賀状書く
馬場繭子
近年年賀状は今年でやめるというのが何枚も来る。来ている賀状でも全部印刷で手書きの部分はほとんどないのが多い。作者は自らが癖文字とは分かっているけれど、少しでも手書をすることで気持を届けたいと考えている。受け取った方もそれは感じていて、相変わらず癖字だなあと言いながらも温もりを覚えるものだ。私も版画とか自作の絵に添えて数行の近況を手書きすることにしている。