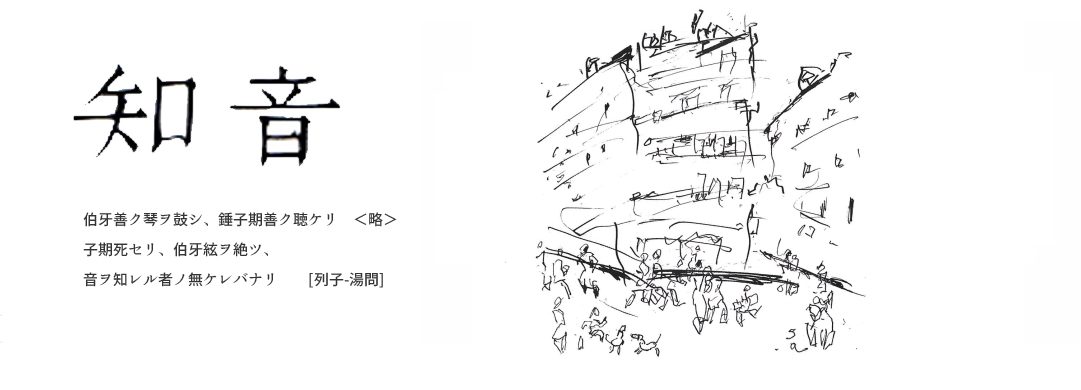足らざるごとく 行方克巳
十本の鉛筆たのみ受験生
受験票すぐ皺々にしてしまふ
うすらひの欠片夕凍みそめしかな
しらうをや十全は足らざるごとく
寒きこと告げしや手話の五指胸に
わらわらと燃えて目刺の目なりけり
焼海苔をばりばりバレンタインの日
独酌のあての如くに春の雪
水 彩 西村和子
菜の花を分け多摩川の大曲り
菜の花や関東ローム層湿し
水彩のまじり気なしの花菜の黄
晴の日も長靴はいて花菜風
菜の花やけんか相手のゐなくなり
菜の花を挿し貧厨に壺ひとつ
菜の花を挿して明るむ流し元
菜の花の茎太々と水を揚げ
しやぼん玉 中川純一
しやぼん玉抱きかかへんと跳ぶ子かな
水替へて目高にそつぽ向かれたる
すれちがひざまの眼差春寒し
冴返る刑死腑分けの場と標し
春ショールダルメシアンを引き連れて
早春や欅の木末雲を梳き
早春や笑めば雀斑のびちぢみ
早春や鏡よ鏡何と云ふ
◆窓下集- 4月号同人作品 - 中川 純一 選
下り立てば夫の待ちゐる雪の駅
吉澤章子
上客に帽子を取りてシェフ御慶
三石知左子
枯野ゆく松明高くかかげばや
井出野浩貴
初旅とて白寿を祝ひ我が許に
村地八千穂
月昇る羽子板市も店じまひ
江口井子
傘の雪しづらせ長き御慶かな
石原佳津子
天辺の星みつからぬ聖樹かな
森山栄子
しみじみと齢を思ふ明けの春
前田星子
竹箒立て掛けてあり大枯木
林 良子
おろかしき遠吠つづく寒夜かな
米澤響子
◆知音集- 4月号雑詠作品 - 西村和子 選
枯園にさつくりと割るカレーパン
米澤響子
ファーブルの貧しき暮らし冬林檎
井出野浩貴
冬銀河ルオーのイエス眉太き
島田藤江
冬晴やゆつくり歩くのは苦手
高橋桃衣
倫敦より明治は遠し漱石忌
藤田銀子
亥の子餅添へ借覧の書を返す
山田まや
島に生き早や十年や波の花
菊池美星
しぐるるやただいまと言ひ灯す部屋
吉田林檎
初神籤誰も日向に開きをり
中津麻美
今時の子はと言ひかけ咳けり
塙 千晴
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
寒林の樹液とくとく星しんしん
米澤響子
「とくとく」は命の鼓動、「しんしん」は広大な夜空と静けさを表す言葉。擬音語とも擬態語ともとれるが、一見枯れ切った木々や動きのない木々の幹の奥に流れる樹液の音を聞きとった。星そのものは音を発しないが、しんしんと冷えてくるとか、しんしんと静まり返ったとか言う場合に用いる表現なので、聴覚ばかりでなく体感にも訴えてくる。
これも写生の一つなのだ。寒中の木々のありようや大気の冴えた様を言葉で描くとこのようになる。音読してみるとその効果が一層わかるだろう。
父のことつくづく知らず冬の月
井出野浩貴
お父さんが亡くなってしばらく時が経ったが、その後の手続きや遺品の整理などを手掛けているうち、一番身近な存在であったはずなのに知らないことばかりだということに気付いたのだろう。その思いを語っているのが冬の月だ。煌々と冷たい光をはなっている冬の月は、他の季節の月よりも遙かに遠い存在だ。思えば私達は両親のことをどれほど知っていただろう。そんなことを読み手に思わせる力がある句だ。別に親子関係がうまくいってなかった訳でもない。むしろ父の思いは誰よりも知っていると思っていたし、その期待に応えても来た。だからこそ亡き今になって、「つくづく知らず」と思い知ったのである。
男性にとっての父を思う俳句と女性にとって母を思う俳句とは、おのずから違ってくる。この句は前者の代表的作品といえよう。
佳き酒の届きし夕蕪鮓
島田藤江
いかにも酒好き、美食家の句だ。自分で買ってきた酒ではなく、地方からおいしい地酒が届いたのだろう。これを楽しむには蕪鮓が一番だ。そう思って蕪鮓は買ってきたのだろう。しかしあくまでも主役は酒、蕪鮓はつまに過ぎない。味覚に訴えてくる心憎い作品だ。