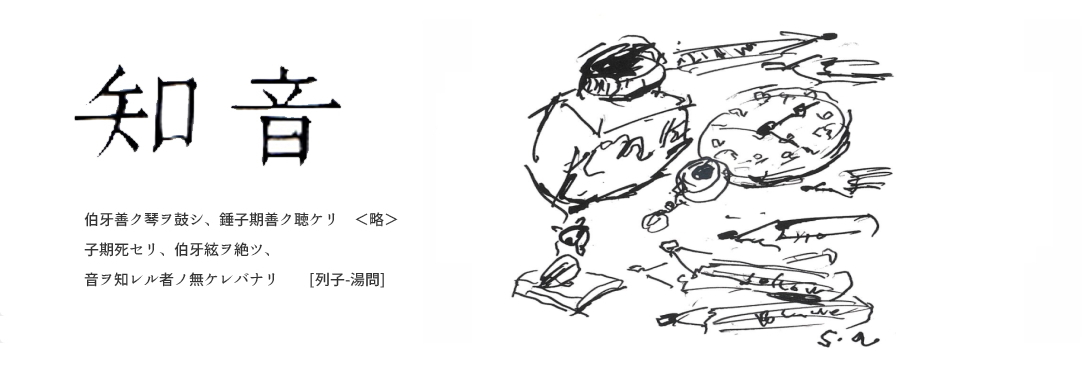内 外 西村和子
太枝を斬られてもなほ初桜
起き直り蕊むくつけき落椿
遠霞望遠鏡を過去へ向け
花の雨寝覚めの床に囁くは
水門の内外平ら春の暮
船溜り名残の落花たゆたへり
少年の臑のすこやか松の蕊
かげろふや忌日過ぎたる虚子の墓
山椒魚 行方克巳
春や春葛根湯のあれば足り
見てよ見て野苺よこのちつこいの
によきによきと建つものは建ち椎若葉
食はずぎらひとは味噌餡の柏餅
はんざきの目のつぶつぶと二つある
コンマ一秒にて山椒魚の餌食
山椒魚盧生の夢の覚めたれば
何もせぬことにも疲れ新茶くむ
花 莚 中川純一
花筵抱へ先頭先頭お父さん
ばんざいは抱つ子の合図花筵
すれすれの燕に池の照り返し
春宵の鎖骨をなぞるレースかな
気まぐれに気まままに咲いて姫女苑
水揺れて赤ちやん目高身構へる
話したき一人隔たり春渚
春宵の言葉どほりにとれば罠
◆窓下集- 6月号同人作品 - 中川 純一 選
ものの芽のこゑを聴かむと跼みけり
青木桐花
縮緬のお座布ふつくら春火鉢
小野雅子
眉山をなだらかに描き春灯
三石知左子
下萌や鳥の刺繍のベビー靴
牧田ひとみ
踊り場に一燭ゆるゝ雛の家
米澤響子
春一番シャガールの馬空を飛ぶ
くにしちあき
泥団子並べてありぬ蝶の昼
松枝真理子
今日よりも明日良からむ蝶生る
小倉京佳
ふる里も東風吹く頃や隅田川
芝のぎく
沈丁の香よころころと笑ふ娘よ
菊田和音
◆知音集- 6月号雑詠作品 - 西村和子 選
春の水鳴り出づ一歩近付けば
小山良枝
春燈や卓の辺に伏す盲導犬
井出野浩貴
寄り付に円座を並べ日脚伸ぶ
山田まや
どこまでもボール転がる草青む
井戸ちゃわん
春の風邪うがひぐすりのすみれ色
牧田ひとみ
本棚の埃見ぬふり春の風邪
影山十二香
撫で牛を帰りにも撫であたたかし
廣岡あかね
宵にまた歩かむ神楽坂の春
志磨 泉
雪掻の力任せは捗ゆかず
石原佳津子
バナナ喰ひつつぼろ市の客あしらひ
磯貝由佳子
◆紅茶の後で- 知音集選後評 -西村和子
胸騒ぎ覚ゆ無数の落椿
小山良枝
椿の花は、首からぼたっと落ちるので不吉だと思われてきたが、花びらが散らずに完全な花の姿のまま落ちるのは、その構造に由来する。落椿を拾って子細に見ると、五弁の花びらと芯が、まるで造化の神が糊付けしたようにきっちりとつながっている。
真っ赤な椿が、咲いていた時の形のままたくさん落ちているのを目にして、「胸騒ぎ覚ゆ」と感じたのは、共感を呼ぶ。主観的写生と言えようか。その底には、客観写生の目が働いていることは言うまでもない。
水の辺になにしか来けむ春の暮
井出野浩貴
「なにしか」は、どうしてかという意味だが、「し」は強めの助詞でことさら意味がない。水辺に来た時、なんでこんなところに来たのだろうと思った。誰にも経験のあることだが、「春の暮」のアンニュイや、妖しい心持と響き合っている。
人間の行動は、全てが自分の意志に従っているわけではない。仕事や用事に追われている時は気づかなかった、我ながら不思議な行動。それは、気分の浮き立つ春の季節感の一つと言えようか。
うららかや子らよぢ上りふら下がり
井戸ちゃわん
音読してみると、ラ行の音の連続が軽やかで効果的である。情景はそこらの公園で遊ぶ子供たちの様子で、目新しいものではない。しかし俳句は、奇異なことがらを詠むことに意味があるのではなく、誰もが見慣れているはずの光景を、季節感と詩心をもって描写することに意味があるのだ。