虫の夜の孤島めきたる机かな
井出野浩貴
「知音」2022年1月号 知音集 より
客観写生にそれぞれの個性を
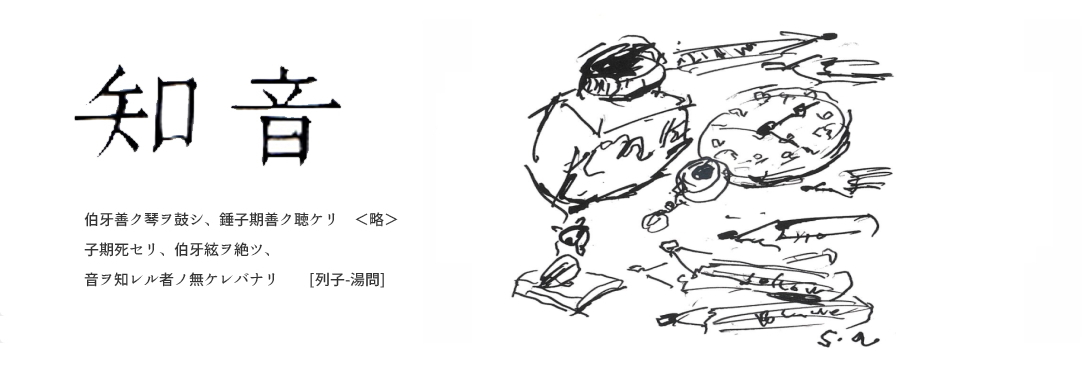
「知音」2022年1月号 知音集 より
「知音」2022年1月号 窓下集 より
「知音」2022年1月号 知音集 より
「知音」2022年1月号 知音集 より
『句集 鎮魂』 角川書店 2010年刊 より
『句集 昆虫記』 角川書店 1998年刊 より
「知音」2021年12月号 知音集 より
「知音」2022年1月号 知音集 より
喉仏大きく動き生ビール
深澤範子
喉仏の動きだけを言うことで、ビールを豪快に飲んでいる様子から、泡の細やかなビールの色、ピッチャーの重量感や冷たさ、喉ごしの清涼感を描き出している。なんとも気分がいいし、生ビールが飲みたくなる句だ。
生ビール、瓶ビール、缶ビールは、中身は違わないのだそうだが、場所柄や雰囲気は違う。昨今は家でも生ビールが飲めるようだが、この句はやはりビアガーデンのようなところを想像したい。(高橋桃衣)
ちぬ釣りや夜間飛行の赤ランプ
辻 敦丸
「ちぬ」は黒鯛のこと。黒鯛は海老や蟹、小魚などを餌にしているので、岸に近い磯や堤防といったところでも釣れる。
この景色は東京湾か大阪湾のような、夜の帷が下りても飛行機は赤いランプを点灯しながら離着陸を繰り返し、街はまだまだ動いているようなところを感じさせる。
そんな夜の片隅で、かたや餌を探している黒鯛と、釣ろうとしている人間・・・海風の涼しい、都会の一夜景である。(高橋桃衣)
急にもの言はなくなりし昼寝かな
西山よしかず
昼食が済んで、テレビを消してちょっと横になり、全くこの頃の世の中はねえとか、いつまで暑さが続くのかねえ、などと取り止めもなく話していた声がぱたっと止まって、眠っている。
夜の就寝だったら、よほど疲れている様子だが、昼寝である。あれ、寝ちゃったなと思った作者も、うつらうつらしている。
気張らずに暮らしている夫婦の夏の一日が見えてくる句。(高橋桃衣)
百年を踏み固めたる土間涼し
牛島あき
こう言われて、なるほどと思った。土間を作る時にも、土を叩いたりして固めて平らにしただろうが、それでも一朝一夕にして現在のようになった訳ではない。
百年の間、外に出て戻って部屋に上がる度に、あるいは炊事や仕事をする度に、この土を踏み固めて来たのだ。土間の石のような固さ、平らかさには、この家の百年の歴史が詰まっている。それを、「百年を踏み固めた」と表現したところが巧みである。
悲喜こもごもの歴史を何も語ることなく、涼しい風を通わせている土間である。(高橋桃衣)
地底より湧き上がりたる蝉時雨
宮内百花
蟬時雨とは、木々でたくさんの蟬が鳴いている様子を時雨に喩えたものだが、作者は蟬時雨が地底から湧き上がっている、と感じた。上から降るだけではなく、地面に反響するほどの声だということだ。それを、「湧き上がりたるかのごとく」などと遠回しに言うのではなく、湧きあがっている、とストレートに言ったことで、声の勢いが感じられ、印象も鮮明となった。蟬の一生を考えると、「地底」という言葉にも説得力がある。(高橋桃衣)
アイスコーヒーすつぽかされたかも知れぬ
森山栄子
喫茶店で待ち合わせているが、時間を過ぎても相手が来ない。氷は溶け、薄くなってしまったアイスコーヒーは、もう飲む気にもならない。そんな不味そうな色も味も、待ち合わせの場所も、撫然とした気持ちもはっきりと読者に伝わってくるのは、「アイスコーヒー」だからこそ。(高橋桃衣)
通信障害復旧未だ街溽暑
長谷川一枝
夕涼み羽田空港指呼のうち
鎌田由布子
七月やいつてきますの声弾み
水田和代
上方の和事よろしき夏芝居
箱守田鶴
校庭に映画の準備夕焼雲
牛島あき
鼻筋に白を引かれて祭の子
黒木康仁
岩のごと牛横たはる大夏野
(岩のごと牛の横たふ大夏野)
若狭いま子
みづうみの端より白雨来たりけり
小野雅子
朝涼し挨拶をして男の子
(朝涼し挨拶をして男子過ぐ)
水田和代
台風の余波の雨音また強し
水田和代
昼寝覚めはや夕刊の届く頃
長谷川一枝
施餓鬼棚飯山盛に供へあり
巫 依子
沢音の夜空へ響く螢狩
小山良枝
宵宮の人垣分けて救急車
松井洋子
まれびとと蛍待つなり橋の上
長谷川一枝
縁てふ字を割つて入る夏暖簾
(縁とふ字を割つて入る夏暖簾)
小山良枝
縞馬に見惚れて汗を忘れけり
松井伸子
短夜や階段上がるハイヒール
岡崎昭彦
掛小屋に四万六千日の風
箱守田鶴
もののふの化身かきらり黒揚羽
鈴木ひろか
青芝や天井高きフランス窓
飯田 静
夏帽子車に映る我ひしやげ
鏡味味千代
顎上げて目を閉ぢてゐる大暑かな
三好康夫
対岸の都心の明かり宵涼し
鎌田由布子
泣き止みし子に見せてやる金魚かな
矢澤真徳
雨上がり晩涼の時賜りし
水田和代
短夜や己が寝言に目覚めたる
(短夜や己が寝言に目覚めたり)
岡崎昭彦
桔梗の紫と白雨上がる
板垣もと子
三絃の音にほたほた凌霄花
(三絃の音にほたほたと凌霄花)
松井洋子
冷さうめん盛大に卓濡らしつつ
小山良枝
下校児の奇声喚声夏に入る
(下校子の奇声喚声夏に入る)
藤江すみ江
青芝に聴くや管楽八重奏
飯田 静
小流れへみな傾ぎたる百合の花
鈴木ひろか
かなかなの声透きとほる雨上がり
鈴木ひろか
通院の五年過ぎたり時計草
鎌田由布子
群れ咲きて寂しさ募る黄菅かな
松井伸子
遠雷やピアノの音色やや変はり
佐藤清子
籐椅子や我と齢を重ねたる
(籐椅子や我と齢を重ねたり)
岡崎昭彦
雨雫湛へ百日紅のフリル
藤江すみ江
大緑蔭少年像は空を指し
鏡味味千代
日除してばた足指導保育園
飯田 静
来年の約束もして螢の夜
小山良枝
初めての俳句指折り夏休み
鏡味味千代
地図持たぬ旅してみたし夏の雲
田中優美子
仮定法過去完了や雲の峰
山田紳介
雀鳴き朝かと思ふ昼寝覚
若狭いま子
療養の朝の検温蝉時雨
飯田 静
星祭母の水茎懐かしき
鈴木ひろか
男でも女でもなしソーダ水
鎌田由布子
水引の裾にふれたり旅衣
西山よしかず
梅雨上がる借りつぱなしの女傘
奥田眞二
酔芙蓉不老も不死も味気なし
荒木百合子
飛行機の発着臨むバルコニー
鎌田由布子
葛切のはかなき色を啜りけり
緒方恵美
こざかしく葉つぱに紛れ子かまきり
長谷川一枝
錆びてなほ回り教会の扇風機
(教会の扇風機錆びてなほ回り)
宮内百花
嬬恋のキャベツどすんと届きけり
牛島あき
四十雀首かしげたる枝の揺れ
鈴木紫峰人
「歴史的仮名遣いは辞書を引いて調べよう」
知音では、歴史的仮名遣いを用います。
五七五の韻律や切れを生かし、余韻ある表現をするには文語が不可欠で、その文語の表記には歴史的仮名遣いがふさわしいと思うからです。
(詳しくは西村和子著『添削で俳句入門』164頁をお読みください。)
今回、「舫いゐる」と表記された句がありました。
「もやう」と国語辞典を引いてみると、
「もやう 舫う モヤフ」
とあります。これは歴史的仮名遣いでは「もやふ(舫ふ)」と書くということです。
「いる」(舫っている、ということですから「居る」の項です)を引いてみましょう。
「いる 居る ヰル」
とあります。この「ヰ」はひらがなでは「ゐ」のことですので、歴史的仮名遣いでは「ゐる」と書きます。
ですので、「舫いゐる」は正確には「舫ひゐる」となります。
同様に「植える」を引くと、「うえる 植える ウヱル」とあります。この「ヱ」は「ゑ」のことで、「うゑる(植ゑる)」と書くということです。
このように、辞書には歴史的仮名遣いがカタカナで記されていますので、辞書を引いて確認する習慣をつけましょう。
なお、カタカナが記されていない言葉は、歴史的仮名遣いと現代仮名遣いが同じであるということです。
高橋桃衣
「知音」2021年12月号 知音集 より